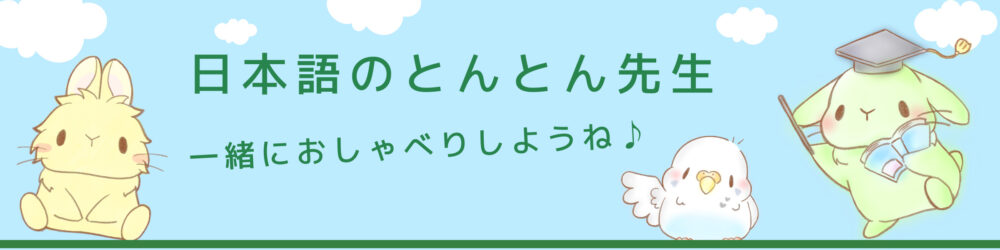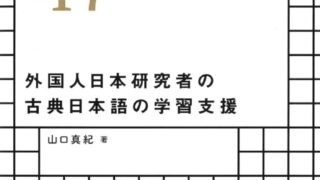2025年3月15日(土)に日本語教育方法研究会に行ってきました。
この研究会は、すべてがポスターでの発表です。
授業や研究に直結した内容が多くて、質疑応答も自由にでき、とても勉強になりました。
AI関連の研究にお客さんが多く集まっている印象でした。
前半・後半の2回のランチ交流会で、ゆっくり交流できたのもよかったです。
特に文字・漢字セクションでの研究や教育実践交流は、熱い思いをもった人が多くて、楽しかったです!
その後、ランチ交流会で知り合った先生の発表を聞きにいったところ、共同研究のメンバーに、古い知り合いの先生がいらっしゃいました。
「あ、吉田さん、お久しぶりです。ここに、引用させてもらっています」
とポスターを指さして、私の研究を紹介していることを教えてくださいました。
こちらのご発表、研究の視座がとても面白いと思いました。
日本語教員は、「教える」仕事以外にも、色々な「管理運営業務」があり、その管理運営業務を見える化し、やり方をシェアすることで効率よく仕事を進めたい、という視点からの研究でした。
(中川健司・角南北斗・平山允子(2025)「日本語教育マネジメントの必要性」日本語教育方法研究会誌 Vol.31 No.2)
私:日本語業界は、授業準備に時間をかけることを良しとするのが、よくないと思う。容量よく短い方がいいのに。
という話から、業務の効率化についての話題についてたくさん情報交換をさせていただきました。
そして、ご紹介いただいたのがこちらの論文
🔹橋本洋輔,中川健司,角南北斗,齊藤真美,布尾勝一郎,野村愛(2017)
「授業準備にまつわる数字を探る-データに基づいたコース運営を目指して-」『日本語教育方法研究会』23 巻 2 号 p. 24-25
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jlem/23/2/23_24/_pdf/-char/ja
この論文の中の、以下の記述、大変共感しました。
以下引用
「時給 2000 円の場合、まず、講師本人にとって、授業 1 時間あたりの授業準備時間が 15 分を超えたあたりから、他職と比較した際の経済的メリットがなくなりはじめ、日本語教育能力検定試験合格といった「専門性を高める」行為の経済的価値が見出しにくくなる。そして、 常勤講師であっても、授業準備時間 30 分を超 えたあたりから生活時間が圧迫され始め、残業代が出ないのであれば経済的損失も出てくる。60 分を超えると、最低賃金に抵触する恐れが出 てくるた 6め、雇用者側にとっても(本来であれ ば)看過できない領域に突入する。 (p .25 太字は筆者)」
また、次のサイトも紹介していただきました。
🔹日本語教員の管理運営業務プロジェクト
https://nihongo-kanriunei.jimdofree.com/
さまざまな立場の日本語教員がより働きやすくなることや、各々の所属組織の運営がより改善されることへの貢献をめざした活動を行っているそうです。
ちなみに、紹介していただいた私の研究は日本語の授業引き継ぎに関する研究です。「ニッチな」研究ですが、こうやって注目していただくことがあると、頑張って書いておいてよかったと嬉しくなります。
吉田美登利(2021)「効果的なチームティーチングに向けた授業引継ぎ記録の分析」『第23回専門日本語教育学会研究討論会誌』pp10-11
吉田美登利(2023)効果的なチームティーチングに向けた授業引き継ぎ記録の分析 アカデミック・ジャパニーズジャーナル15号pp.1-9
引き継ぎ記録の書き方の研究がすすみ、日本語教育を学ぶ学生たちも、記録の書き方をきちんと教えてもらえれば、そのメリットは、日本語学習者も教授でき、日本語教育全体がよりよくなっていくと考えています。
日本語そのものの研究以外にも、このような、業務に関連する研究も進んでいくといいなと思っています。